| 修正箇所 |
誤) |
正) |
修正適用 |
| P18 表1-1 |
【横弾性係数E】 【縦弾性係数G】 |
【縦弾性係数E】 【横弾性係数G】 |
未定 |
P69
κの式の補足 |
c:ばね係数 |
c:ばね指数 |
未定 |
P102
κの式の補足 |
c:ばね係数 |
c:ばね指数 |
未定 |
★
P105
下から5行目 |
①ステンレス鋼線の場合は、鋼線の初応力の15%減とします。
②りん青銅線、黄銅線、洋白線の場合は、鋼線の初応力の50%減とします。
③ばね成形後に低温焼きなましを実施する場合は、上記で求めた値に対して、さらに鋼線で20~35%減、ステンレス鋼線で15~25%減とします。 |
①ステンレス鋼線の場合は、鋼線の初応力の15%減とします。
②りん青銅線、黄銅線、洋白線の場合は、鋼線の初応力の50%減とします。
※上記の①と②はグラフから読み取る場合にのみ適用し、簡易式には適用しません。
③ばね成形後に低温焼きなましを実施する場合は、上記で求めた値に対して、さらに鋼線で20~35%減、ステンレス鋼線で15~25%減とします。 |
未定 |
P122
中断枠内の式 |
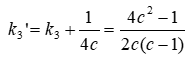 |
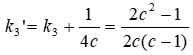 |
未定 |
P123
中断枠内
1行面 |
B部の最大曲げ応力の式 |
B部の最大せん断応力の式 |
未定 |
P123
中断枠内
4行面 |
B部の最大曲げ応力は~ |
B部の最大せん断応力は~ |
未定 |
★
P145
図7-11の下側にある本文 |
初応力τi“は鋼線の値であり、今回材質はステンレス鋼線を選択したため、初応力を15%減、つまり、計算結果の85%と補正します。
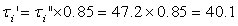 〔N/mm2〕 〔N/mm2〕
ステンレス鋼線を成形後、低温焼きなまし処理をすることから、τi‘をさらに20%減とします。
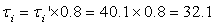 〔N/mm2〕 〔N/mm2〕
よって、初張力は下式で求められます。
初張力: 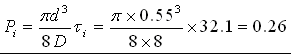 〔N〕 〔N〕
この値は、本章第②項で目安とした初張力とほぼ同じであることが確認できました。 |
ステンレス鋼線を成形後、低温焼きなまし処理をすることから、τi‘を20%減とします。
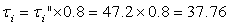 〔N/mm2〕 〔N/mm2〕
よって、初張力は下式で求められます。
初張力: 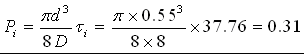 〔N〕 〔N〕
この値は、本章第③項で目安とした初張力と若干違う値となりました。 |
未定 |
★
P146
表内の左下 |
|
|
未定 |
★
P146
上から7行目 |
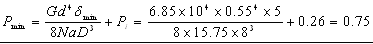 |
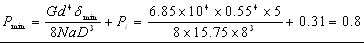 |
未定 |
★
P146
上から8行目 |
仮パラメータで確認すると、ばねの目標である荷重P=0.7〔N〕に対して、±10%以内に入っているため、これでOKとします。 |
仮パラメータで確認すると、ばねの目標である荷重P=0.7〔N〕に対して、0.1〔N〕大きめにできましたが、安全率を見込んでいるのでOKとします。 |
未定 |
★
P146
上から14行目 |
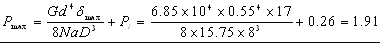 |
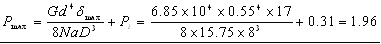 |
未定 |
★
P149
下から5行目 |
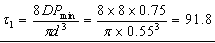 |
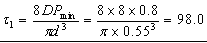 |
未定 |
★
P149
下から1行目 |
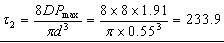 |
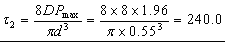 |
未定 |
★
P150
下から7行目 |
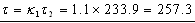 |
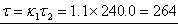 |
未定 |
★
P150
下から3行目 |
「使用上の最大せん断応力」=534.4〔N/mm2〕 τ=257.3〔N/mm2〕 より、
|
「使用上の最大せん断応力」=534.4〔N/mm2〕 τ=264〔N/mm2〕 より、
|
未定 |
★
P151
上から6行目 |
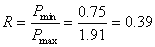 |
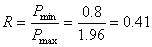 |
未定 |
★
P151
上から7行目 |
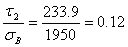 |
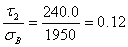 |
未定 |
★
P151
図7-14 |
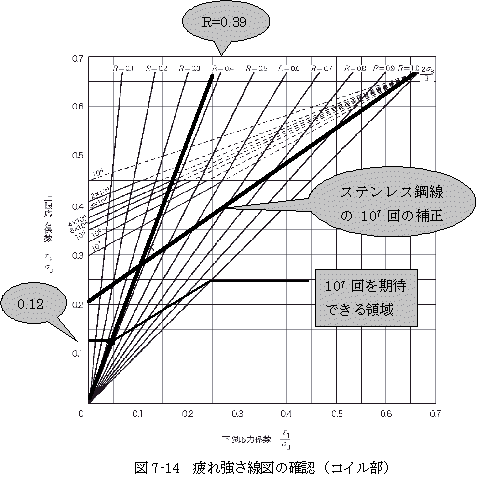 |
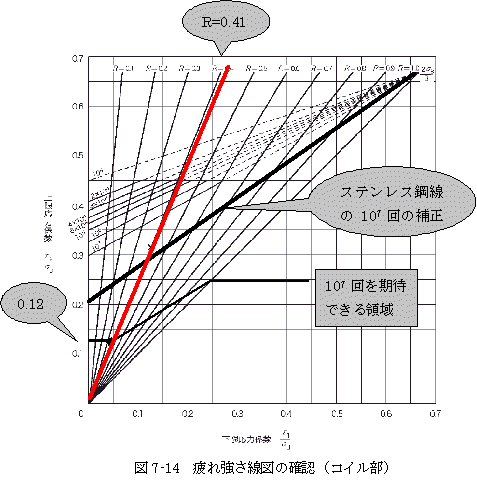 |
未定 |
P153
κ1'の式 |
κ1’の「’」が間違い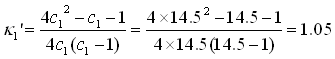 |
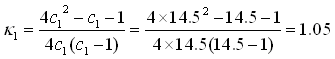 |
未定 |
P153
κ1'の式を追加 |
- |
上記κ1の下に式を追加
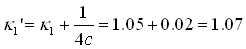 |
未定 |
★
P153
σFAの式 |
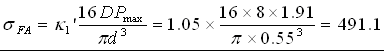
|
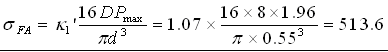 |
未定 |
★
P153
下から4行目 |
σFA=491.1 |
σFA=513.6 |
未定 |
★
P154
上から6行目 |
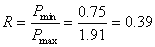 |
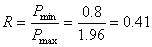 |
未定 |
★
P154
上から7行目 |
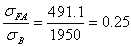 |
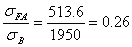 |
未定 |
★
P154
図7-17 |
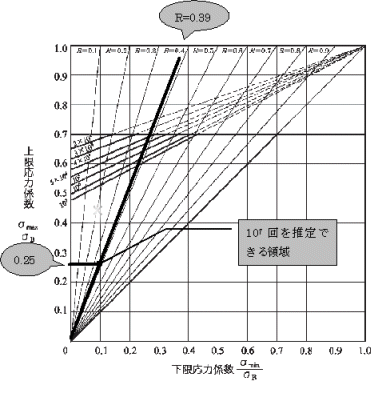 |
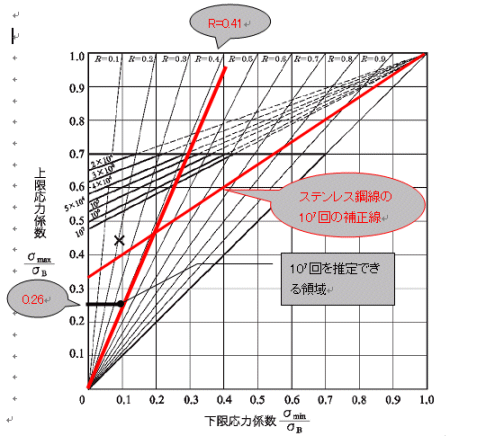 |
未定 |
★
P154
図7-17の
上に文章追加 |
- |
フックA部は曲げ応力を受けるため、材料係数は後述するP185の6行目に示すようにステンレス鋼線の場合、0.32を採用し補正する。 |
未定 |
★
P156
下から8行目 |
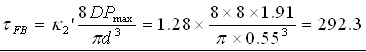 |
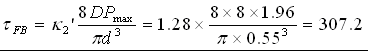 |
未定 |
★
P156
下から4行目 |
 |
 |
未定 |
★
P157
上から4行目 |
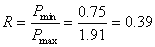 |
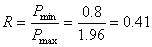 |
未定 |
★
P157
上から5行目 |
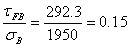 |
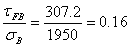 |
未定 |
★
P157
図7-19 |
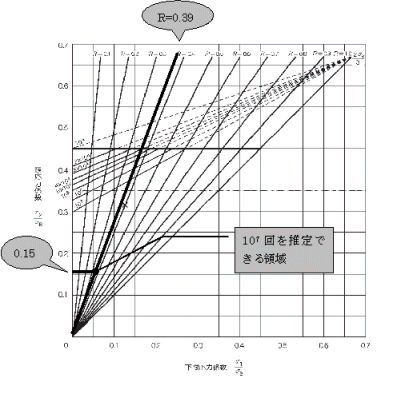 |
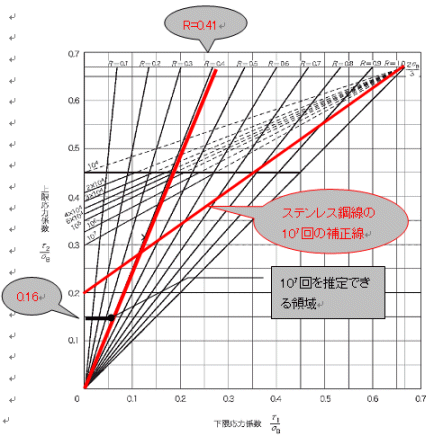 |
未定 |
★
P159
右上の数値 |
荷重 1.91N
荷重 0.75N |
荷重 1.96N
荷重 0.8N |
未定 |
★
P159
中央の表 |
| 初張力 |
N |
(0.26) |
常
用 |
荷重時の長さ |
mm |
29.1 |
| 荷重 |
N |
0.75 |
動
作 |
荷重時の長さ |
mm |
41.1 |
| 荷重 |
N |
1.91 |
|
| 初張力 |
N |
(0.31) |
常
用 |
荷重時の長さ |
mm |
29.1 |
| 荷重 |
N |
0.8 |
動
作 |
荷重時の長さ |
mm |
41.1 |
| 荷重 |
N |
1.96 |
|
未定 |
★
P160
表の上から12行目 |
|
|
未定 |
★
P160
表の上から15~16行目 |
| 最小荷重 |
Pmin= |
0.75 |
〔N〕 |
| 最大荷重 |
Pmax= |
1.91 |
〔N〕 |
|
| 最小荷重 |
Pmin= |
0.8 |
〔N〕 |
| 最大荷重 |
Pmax= |
1.96 |
〔N〕 |
|
未定 |
★
P160
表の上から25~26行目 |
| 最小荷重でのせん断応力(コイル部) |
τ1= |
91.8 |
〔N/mm2〕 |
| 最大荷重でのせん断応力(コイル部) |
τ2= |
233.9 |
〔N/mm2〕 |
|
| 最小荷重でのせん断応力(コイル部) |
τ1= |
98.0 |
〔N/mm2〕 |
| 最大荷重でのせん断応力(コイル部) |
τ2= |
240.0 |
〔N/mm2〕 |
|
未定 |
★
P160
表の上から29行目 |
| 繰り返し荷重を受ける最大せん断応力 |
τ= |
257.3 |
〔N/mm2〕 |
|
| 繰り返し荷重を受ける最大せん断応力 |
τ= |
264 |
〔N/mm2〕 |
|
未定 |
★
P160
表の上から33~34行目 |
| 応力修正係数(A部) |
K1’= |
1.05 |
|
| 最大荷重での曲げ応力(A部) |
σFA= |
491.1 |
〔N/mm2〕 |
|
| 応力修正係数(A部) |
K1= |
1.07 |
|
| 最大荷重での曲げ応力(A部) |
σFA= |
513.6 |
〔N/mm2〕 |
|
未定 |
★
P160
表の上から38行目 |
| 最大荷重でのせん断応力(B部) |
τFB= |
292.3 |
〔N/mm2〕 |
|
| 最大荷重でのせん断応力(B部) |
τFB= |
307.2 |
〔N/mm2〕 |
|
未定 |
★
P160
表の上から41~44行目 |
| 応力比 |
R= |
0.39 |
| ・コイル部 |
上限応力係数 |
|
0.12 |
| ・フック部A |
上限応力係数 |
|
0.25 |
| ・フック部B |
上限応力係数 |
|
0.15 |
|
| 応力比 |
R= |
0.41 |
| ・コイル部 |
上限応力係数 |
|
0.12 |
| ・フック部A |
上限応力係数 |
|
0.26 |
| ・フック部B |
上限応力係数 |
|
0.16 |
|
未定 |
P166
表8-1 |
|
|
未定 |
P172
dsの式 |
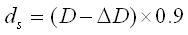 |
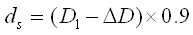 |
未定 |
P172
dsの式の横 |
ds:コイル内径部に設置する軸径 |
ds:コイル内径部に設置する軸径
D1:コイル内径 |
未定 |
P175
10行目 |
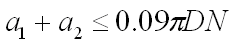 |
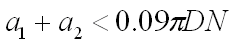 |
未定 |
P183
κbの式の補足 |
c:ばね係数 |
c:ばね指数 |
未定 |
P196
dsの式 |
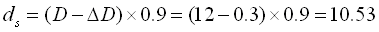 |
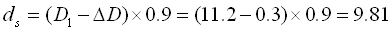 |
未定 |
P196
下から5行目 |
計算上で推奨される案内棒の直径が10.53〔mm〕となり、当初の案内棒径10〔mm〕でも問題ないレベルと判断できます。
ここで、案内棒径の計算値が、実際の案内棒径より小さくなる場合や、逆に隙間が大きすぎる場合は、コイル径を変更して再調整するか、案内棒径の変更を検討します。 |
計算上で推奨される案内棒の直径が9.81〔mm〕となり、当初の案内棒径10〔mm〕では問題がある可能性があり、案内棒径を9.8〔mm〕にしなければいけません。
このように、案内棒径の計算値が、実際の案内棒径より小さくなる場合や、逆に隙間が大きすぎる場合は、コイル径を変更して再調整するか、案内棒径の変更を検討します。 |
未定 |
P202
要目表の中 |
|
|
未定 |
P203
中段 |
ds=10.53
ds’=10 |
ds=9.81
ds’=9.8 |
未定 |